1940年、日独伊三国同盟が締結される。
日独伊三国同盟とは?
日独伊三国同盟(にちどくいさんごくどうめい)は、1940年(昭和15年)9月27日にベルリンの総統官邸(そうとうかんてい)で調印(ちょういん)された日本、ドイツ、イタリアの軍事同盟(ぐんじどうめい)。正式名称は、「日本国、独逸国及伊太利国間三国条約」。
日独伊三国同盟の主な内容は?
1.相互の影響圏の尊重
日本はドイツとイタリアのヨーロッパにおける新秩序建設(しんちつじょけんせつ)(しんちつじょけんせつ)の指導的地位(しどうてきちい)(しどうてきちい)を認め、逆にドイツとイタリアは日本の大東亜(だいとうあ)における新秩序建設(しんちつじょけんせつ)の指導的地位(しどうてきちい)を認めるとした。
2.相互援助の約束
三国のいずれかが、当時のヨーロッパ戦争や日中戦争(にっちゅうせんそう)に参加していない国(主にアメリカを指す)から攻撃を受けた場合、三国は政治的(せいじてき)・経済的(けいざいてき)・軍事的(ぐんじてき)に援助することを約束した。
3.ソ連との関係維持
三国とソ連との政治的(せいじてき)関係には影響を与えないことを確認する条項(じょうこう)も含まれていた。
日独伊三国同盟成立の背景は?
日独伊三国同盟(にちどくいさんごくどうめい)は、突然成立したものではなく、その前提(ぜんてい)として1936年の日独防共協定(翌37年に日独伊三国防共協定に拡大)があった。
当初は、反共産主義(反ソ連)を掲(かか)げた協力関係だったが、第二次世界大戦(だいにじせかいたいせん)の展開とともに、より強固(きょうこ)な軍事同盟(ぐんじどうめい)へと発展した。
特に、1940年6月にドイツ軍がフランスを降伏(こうふく)させ、ヨーロッパでの勢力(せいりょく)を拡大していた時期でした。日本はこの「バスに乗り遅れるな」という世論(よろん)に後押しされ、南進政策(なんしんせいさく)を進めるためにもドイツ・イタリアとの同盟に踏み切った。
日独伊三国同盟の目的と意図は?
日独伊三国同盟(にちどくいさんごくどうめい)の主な目的は以下の3点にあった。
1.アメリカの参戦抑止
1/特に三国がお互いに軍事援助(ぐんじてきえんじょ)を約束することで、アメリカの欧州戦争(おんしゅうせんそう)や日中戦争(にっちゅうせんそう)への介入(かいにゅう)を抑止(よくし)しようとした。
2.日本にとっての意義
長期化(ちょうきか)していた日中戦争(にっちゅうせんそう)の打開(だかい)と、東南アジアへの進出(資源獲得)を図ることだった。
3.ドイツ・イタリアにとっての意義
日本との軍事同盟(ぐんじどうめい)によってアメリカのヨーロッパ戦線(せんせん)への介入(かいにゅう)を抑止(よしく)することを狙った。
日独伊三国同盟の結果は?
皮肉(ひにく)なことに、この日独伊三国同盟(にちどくいさんごくどうめい)は当初の目的とは逆の結果をもたらすことになった。
アメリカの参戦(さんせん)を抑止(よくし)するどころか、むしろアメリカを刺激し、日米対立(にちべいたいりつ)を深め、1941年12月の太平洋戦争開始(たいへいようせんそうかいし)へと導く一因(いちいん)となった。
さらに、ヨーロッパの戦争とアジアの戦争を結びつけ、第二次世界大戦(だいにじせかいたいせん)をアジアに拡大させる結果となってしまった。
最終的には、三国とも敗北(はいぼく)し、日本は、無条件降伏(むじょうけんこうふく)に追い込まれた。
歴史家からは「日本にとって日独伊三国同盟(にちどくいさんごくどうめい)の締結(ていけつ)は、太平洋戦争(たいへいようせんそう)という敗戦(はいせん)への道に向かっていく上で、ポイント・オブ・ノー・リターン(もう引き返せない地点)となった」と評価(ひょうか)されている。
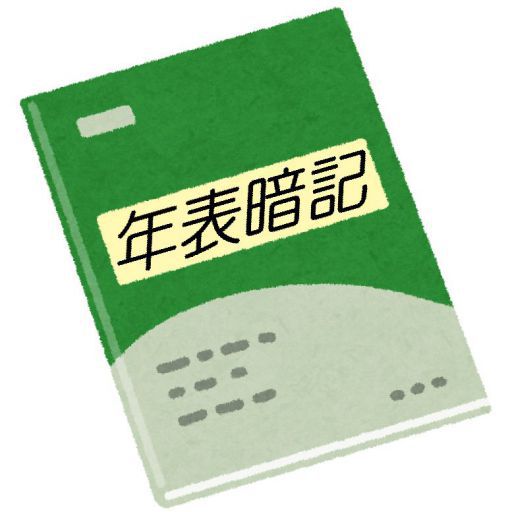


コメント